- 文字サイズ
-
- 標準
- 拡大
- 背景色
-
- 白
- 黒
- 青


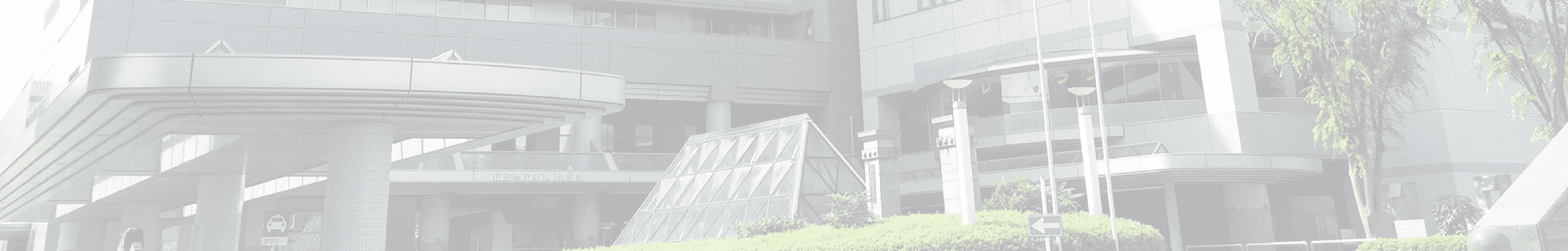
臨床検査室とは、患者さんの病気の診断や治療を行うため、また経過を観察するために、その時の傷病の状態を正しく評価するための検査です。業務は専門性により5つの分野(血液係、生化学係、細菌係、病理係、生理係)に分かれており、各検査のエキスパートが担当しております。また、当直業務により、24時間体制で救急業務に広く貢献しています。
また、感染制御チーム(ICT)、抗菌薬適正使用支援チーム(AST)、栄養サポートチーム(NST)、糖尿病チーム(DCT)、認知症ケアチームのチーム医療にも参画しています。
**当院は、日本臨床衛生検査技師会と日本臨床検査標準協議会が認証する「品質保証施設認証」を取得しています。質の高い臨床検査の提供を目指しています。
1.血液係 2.生化学係 3.細菌係 4.病理係 5.生理係
血液中の細胞(白血球・赤血球・血小板など)数や形態の検査、または血液の凝固・線溶検査などを行っています。

血液の液状成分(血清)や尿、便、髄液、精液、体腔穿刺液(胸水、腹水、心嚢液)などの検査を行っています。健康状態の把握や病気の診断、治療効果などを推測するのに必要不可欠です。

感染症の原因菌を探し、適切な治療薬を調べるのが主な仕事です。大きく分けると、次の5項目の検査を実施しています。

病理検査は、手術や内視鏡検査などで採取した組織を診断する「組織診検査」と痰・尿・子宮擦過物などの細胞を調べる「細胞診検査」があります。
人間の様々な生体機能を検査します。心電図、肺機能、脳波、神経伝導検査、平衡機能、睡眠時間無呼吸検査、超音波検査などの検査を行っています。
| 医師 氏名 | 所属学会 | 履歴 |
|---|---|---|
| 大竹 浩也 | 日本病理学会 (専門医・病理専門研修指導医) 日本臨床細胞学会(専門医) |
H7年 山形大学卒 H13年 東北大学大学院修了(医学博士) |